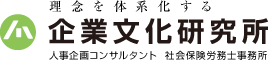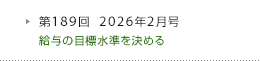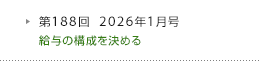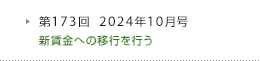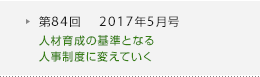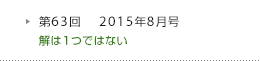はじめに
5月です。多くの会社が人事評価の季節を迎えていることでしょう。人事評価には莫大なエネルギーが投入されています。しかし、それが人材育成のためにどれだけ活用できているか?というと、十分でない会社も多いことと思います。成果主義、信賞必罰主義の立場から給与に差をつけることだけが人事評価の目的となっているとしたら、それは人余り時代の人事制度の運用といえるでしょう。人材資源に限りがある現在、人材育成こそ人事制度の第一の目的であると考えます。
そこで今回は、人材育成の基準となる人事制度のあり方について考えてみたいと思います。
具体例
人事制度の3つの柱のうち、人材育成に最も深く関係するのは人事評価制度です。この中身をどのように構築、運用するのかが評価の結果を人材育成に活かせるか否かの分かれ目となります。以下いくつかの具体例を紹介します。
必要最小限度の例

どのような人材に育ってほしいのか?自社独自の考えに基づいて定めたのが人事評価の基準です。評価段階は会社によって5段階、4段階、3段階など様々な場合がありえます。人事評価の基準を満足することができていないと評価される場合には、必ず「どうすればもっと良くなるのか?」という本人にとっての課題があるはずです。この課題を上司が部下に与え、部下がそれを乗り越えることによって人材育成は実現していきます。この一連の流れを最小限度内容としたものが上記の例です。多くの会社ですでに取り入れられていることと思いますが、上司の能力によって与える課題の質が大きく異なってしまうことが難点です。課題とは日々の仕事の中で何をすべきかが部下にとってよくわかるものである必要がありますが、単なる問題点の指摘や叱責に終わってしまっては人材育成にはつながりません。
上記の難点を補う例
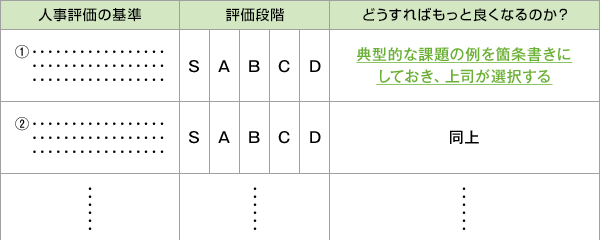
上司の能力によって与える課題の質が大きく異なってしまうことをある程度防ぐことができます。評価段階 「S」 「A」 「B」 「C」 「D」 ごとの定義をできる限り具体的に定めておく方式などもこの例の変形パターンということができます。部下の立場から見た場合、具体的な努力目標がわかりやすくなります。ただし、新しい企画を立てたり、状況に応じた高度な判断が求められる業務や立場(職位)については限界があります。その本人にとっての課題をあらかじめ具体的に想定しておくことは困難になるからです。
PDCAを活用する例
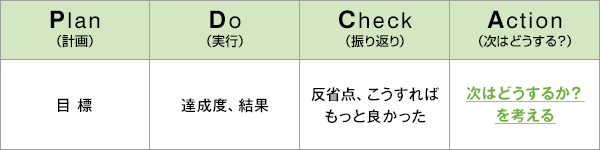
新しい企画を立てたり、状況に応じた高度な判断が求められる業務や立場(職位)については最も適したしくみであると考えられます。自ら課題を見つけ、それを乗り越える手段について仮説を立て (P)、実行し (D)、その結果を検証し (C)、当初の仮説を洗練していく (A) 過程を通じて能力が高まっていくからです。ただし、本人がそのような能力を十分備えていない場合には上司の助言、手助けが必要となります。ここでも最終的には上司の能力に依存せざるをえないという難点が残ってしまうのです。リーダーとはこの P → D → C → A を正しく回転させられる人といってもよいでしょう。このリーダーとしての能力を備えた人材をどれだけ育成することができるか?全社の人材育成の成否は最終的にはこの点にかかっていると考えます。
まとめ
今回は人材育成の基準となる人事制度のあり方について考えてみました。すべての場合に有効な万能薬のようなものはありえませんし、全社共通のしくみとしなければならない理由もありません。それぞれの会社の現状や同じ会社内であっても部門や職種、階層などに応じて最も適切な人事評価制度を開発することが正しい解答であるといえるでしょう。