はじめに
「人事考課(評価)基準」と聞いて真っ先に頭に浮かぶのは“昇給や賞与の査定基準”ということでしょう。しかし、「なぜそもそも昇給や賞与に査定結果を反映させるのか?」と掘り下げていきますと、“会社への貢献度の高さに比例した金銭処遇を与えることで、会社に貢献してもらえるように方向付けること”という結論に辿り着きます。従って、この観点からは「会社への貢献度をいかに正しく測定するか」という点に力点を置いて人事考課(評価)基準のあり方を考えることとなります。
人事考課(評価)基準のあり方を考えるにあたって、この観点は“社員の公正な処遇”を実現するうえで絶対必要なものです。ただし、この観点だけから人事考課(評価)基準のあり方を考えるというのは大変もったいないことです。
今回は「人事考課(評価)の基準を通じて仕事の“型”を示す」と題しまして、人事考課(評価)基準をより多面的な観点から設定、活用することが事業活動に与えるメリットについて解説したいと思います。
よろしくお願いいたします。
人事考課(評価)基準の3つの機能
人事考課(評価)基準には「はじめに」で述べた昇給や賞与の査定基準というほかにも次の機能があるものと考えます。
仕事をしていくうえで「何が正しく」「何が正しくないのか」を判断する基準のことです。
これがないと社員は判断に迷うこととなります。どんな会社にも実際には自然に形成された風土、社風が存在しますので、明文化されたものがなくても社員は自然とこの基準に則った判断、行動をしています。しかし、風土、社風には「固い」「ゆるい」があり、また自然にまかせていてはどうしても「楽な方へ楽な方へ」と崩れていきます。
自社の理念に照らしてこの価値判断の基準をはっきりと示し、強固な企業文化を形成することはトップにしか成し得ない仕事です。また、優れた企業文化というものは容易に他社が真似ることができるものではありません。この企業文化こそ継続的に高い価値を生み出し続ける力の源泉であると考えます。
「社員教育体系」を設定している会社は数多く存在しますが、この教育体系と人事考課(評価)基準との連動がきちんと図られているというのは少数ではないでしょうか。社員教育の目的は自社にとって有為な人材を育成することですので、両者の間にはきちんと連動が図られているというのが本来の姿です。
詳細については人事用語解説の「社員教育」をご覧ください。
なお、1.の価値判断の基準については次の視点を絶対に忘れてはいけません。

「どのようなときに仕事のやりがいを感じますか?」と聞かれて、「お客様から喜ばれたとき」「ありがとうと言われたとき」というのは多くの働く人たちの実感でしょう。これは「自分は社会から必要とされている」「役に立っている」ということの実感→体験であり、人間の本質であると言ってもよいと思います。金銭処遇だけでこの実感を伴わないことを誘導しようとしても長続きしないか、持てる能力の半分も発揮しないのではないでしょうか。
人事考課(評価)基準のあり方
このように考えますと、人事考課(評価)基準のあり方は次のとおり整理することが適切でしょう。
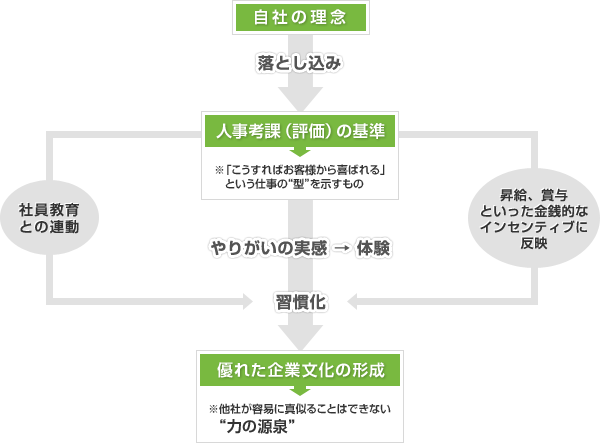
まとめ
人事考課(評価)の基準を昇給や賞与の査定基準としてだけでなく、より多面的な観点から設定、活用することによって一石二鳥も三鳥もの効果が得られることがご理解いただけたら幸いです。みなさんの会社の人事考課(評価)基準をご覧になられて、「自社の基本的な価値観が網羅されているかどうか」を点検してみるとよいでしょう。
次回は給与(報酬、賃金)に関する個別テーマを取り上げます。ご期待ください。


































































































































































































