はじめに
給与(賃金)制度の改定により基本給や手当の水準が上昇することがあります。新しい給与制度への移行は社員一人ひとりを新しい基本給や手当のルールに当てはめることによって実現されます。このときに生じる基本給や手当の上昇額の総計のことを持ち出しと呼びます。

持ち出しがほとんど生じない場合もありますが、持ち出しを伴う給与制度の改定を行うこともあります。その場合にはあらかじめ持ち出しの予算を定めておき、その予算の範囲内とするように新給与の設計を行うことが必要です。そうしなければ実行段階になってから「やはり実行できない」ということになるからです。
そこで今回は持ち出しを予算の範囲内とするように給与制度を設計するためのポイントについて取り上げてみたいと思います。
ポイント1:資格・等級別の基本給の下限金額にいつも注意しておく
資格・等級とは社員の処遇の高さを決める判断軸のことであり (詳しくは2020年11月号で解説しています)、基本給はこの資格・等級ごとに水準が設定されます。

このときポイントとなるのが資格・等級別の基本給の「下限」金額です。
この下限金額が現行比高くなればなるほど持ち出しは上昇します。
新給与の設計にあたって理屈が通っていることは重要ですが、現実に実行できなければ全く意味がありません。

ポイント2:初任管理職の給与水準がどうなるのかにいつも注意しておく
初任管理職とは初めて管理職になった人のことを指します。
管理職になると残業手当や休日出勤手当が支給されなくなる、ということは多くのみなさんがご存知のことと思います。
ただし、労働基準法上管理職として認められるためにはいくつか条件があります。そしてその中の1つに 「給与面での優遇」 があります (詳しくは2012年4月号で解説しています)。
「給与面での優遇」 に当てはまるかどうかについて絶対的な数値、金額基準を示した判例や通達はありません。
そこで、給与設計の実務上は

を確保できるように作業を進めていくこととなります。

、ということです。
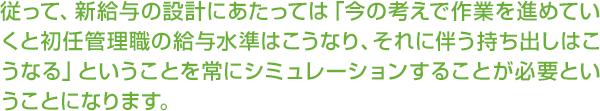
まとめ
「人事・給与制度を改定したが、実際には導入できなかった」 「評価制度まではなんとか導入できたが給与制度は導入できなかった」 という例もよく目にすることです。



































































































































































































