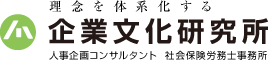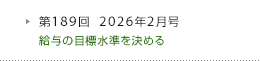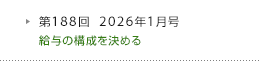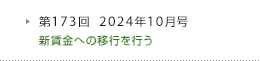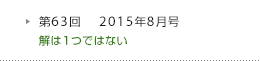はじめに
「定期昇給」という言葉に代表されるように、会社で働く人たちにとって給料は毎年上がるもの、という意識が長い間定着していました。しかし、現在では「給料が上がらない」「給料が下がった」という言葉もよく聞かれるようになりました。売上や利益が伸び悩む中で従来の昇給制度を維持することができない会社が増加しているものと考えられます。
そこで今回は「昇給制度のあり方について考える」と題しまして、“自社における最も適切な昇給管理手法の考え方”について解説します。
よろしくお願いします。
なぜ昇給させるのか?
まず最初に「なぜそもそも昇給させるのか?」について考えます。
多くの企業、特に採用市場において“買い手優位”に位置づけられる企業ほど新卒を中心とした若年層に対する採用意欲が強いというのが実態です。大卒の採用内定率が大きく落ち込む中で「卒業後3年間は“新卒扱い”にしてほしい」と政府が要望を出していることからもこのことは明らかです。「新卒者を採用して中長期の雇用を前提としながら内部で育成していく」というのが働き方や賃金のあり方に強い影響力を持つ企業の基本的な姿勢なのです。
この場合、毎年給料を上げていく昇給制度は原則的には必要ですし、また合理的でもあります。その理由は次のとおりです。
このように考えますと、
会社や部門においては、定期昇給制度は不要ですし、また必要性を感じる経営者もいないものと考えられます。しかし、このようなケースは特定の業種や理念を持った会社に限られるというのが実態であり、大部分の会社では昇給制度は必須のしくみである、といえるでしょう。
賃金表(昇給管理表)の必要性
給料、中でも基本給(基礎的賃金)の昇給管理ツールとして幅広く採用されているしくみとして賃金表(昇給管理表)があります。具体的な中身は様々なものがありますが、毎年の人事考課(評価)の結果に応じて新しい基本給額を決定する表、という点では共通です。
賃金表を設定することにより、次のようなメリットが得られます。

このうち2については、月例給与は賞与とは異なり、一回限りの支給ではないため、毎年の会社業績によって昇給額に格差が生じた場合には後々まで尾を引く、という点で重要な視点であることは確かです。しかしこのことは一方で、“全社員の人事考課(評価)の結果が確定すれば自動的に昇給に必要な原資も決まってしまう”、ということを意味します。15〜20年ほど前までの経済・社会環境下では、この“昇給に必要な原資”は十分に確保できたでしょうし、またこれに加えてベース・アップを行うことも広く一般に行われていました。しかし、現在は<はじめに>でも述べたように「給料が上がらない」「給料が下がった」と言われる時代です。このような企業においては賃金表があったとしてもその実施を凍結しているものと考えられます。
賃金表を用いない昇給管理の方法
<なぜ昇給させるのか?>でも述べたように、昇給させる理由は「生計費の上昇に見合った給料を支給する必要」と「モチベーションを維持する必要」の2つです。この2つが実現できれば必ずしも賃金表の設定にこだわる必要はないのです。
それぞれについて考えてみます。

30歳(例)までは従来の年齢給のように自動的に昇給していく要素を給与体系の中に取り入れる反面、その後は各資格・等級ごとに基本給の下限・上限金額だけを定め、同一資格・等級内での昇給額は毎年の会社業績と照らし合わせて随時決定する。
上記の考え方のポイントを整理すると次のとおりです。

なお、この“自社おける最低保証水準”をどの程度とするかは各社の実態をふまえたうえで決定します。また、必ずしも「年齢給」にこだわる必要はありません。「一定の資格・等級まではほぼ全員が昇格する」という運用を行っている会社も多いと思いますが、意味は全く同じこととなります。

すでに自社における最低保証水準はクリアーしているのですから、後は“昇給原資がどれだけ用意できるかから考える”というのは経営上むしろ当然といえます。

同一資格・等級内での毎年の昇給額は会社業績に応じて変動しますが、昇格したときの最低保証水準は全員一律となるため、社員から見たときの不透明感はなくなります。
まとめ
賃金表(昇給管理表)を用いた昇給運用が行える会社であれば当面はその方式を維持することでよいかもしれません。しかし、「賃金表はあるがその実施を何年間も凍結している」という会社や、「賃金表が全く形骸化してしまっている」という場合には、別の昇給管理システムを構築する必要があるでしょう。その状態を長期間放置しておくと“最近入社した若年層の社員の賃金水準が標準的な生計費を大きく下回る”事態を招いたり、“社員が将来展望を描けない”、“モチベーションの低下を招く”、などの事態を生じかねません。
次回は社員教育に関する個別テーマを取り上げます。
お楽しみに。